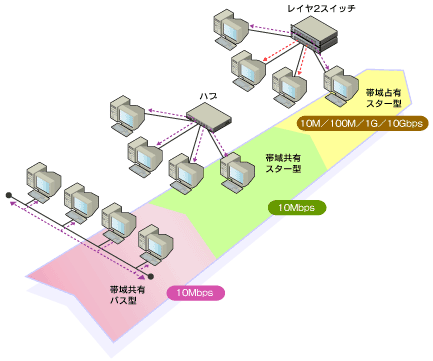
特集:10ギガビット・イーサネット大解剖

標準化の完了した最新イーサネット規格
特集:10ギガビット・イーサネット大解剖
| ギガビット・イーサネットの10倍の速度を誇る、10ギガビット・イーサネットの標準化が完了した。すでに先行して製品出荷を行っているメーカーもあるが、この標準化を機会に、より多くのメーカーが対応してくることになるだろう。今回の10ギガビット・イーサネットでは、CSMA/CDの事実上の廃止やWANへの対応など、高速化が中心だったこれまでのイーサネットの進化とは別の方向性を見せ始めた。本特集では、新たな進化の方向性を見せ始めた、10ギガビット・イーサネットの仕組みや最新情報、今後の展望について解説していく。 |
| Part.1 進化するイーサネット |
イーサネットがネットワークの基盤技術としてここまで浸透するとは、誰が予想しただろうか。イーサネットも、かつてはLANを実現する1つの方式にすぎなかった。現在では、企業のイントラネット・トラフィックの80%以上がイーサネットから発信されているといわれ、もはやLANの世界はイーサネット抜きには語れない。また、多くの通信事業者のネットワークにもイーサネット技術が用いられ、企業向けにイーサネットを広域に接続する通信サービスも提供されている。イーサネットがLANだけでなく、MAN(Metro Area Network)/WANを含めたネットワーク全体を構成するために、必要不可欠な技術となってきたのだ。これほどまでにイーサネットが市場に受け入れられた理由として、常に「最もコストが安く」「最も高速で」「最も簡単な技術」として進化してきたことが挙げられる。
もともとイーサネットは、同軸ケーブルを用いた10Mbpsの帯域を共有するバス型の構成からスタートした。当初のイーサネットではデータの衝突が発生する仕組みだったため、実際の使用効率は10Mbpsの30%にも満たなかった。また、衝突を検出するために伝送距離にも制限があった。配線の面からも決して使い勝手が良いとはいえなかった。ところが、電話回線と同じツイスト・ペア・ケーブルとハブを用いたスター型の構成が可能となったことで、一気に使い勝手が向上した。それに、全二重イーサネットを用いたレイヤ2スイッチの登場や、100メガビット・イーサネットの登場が続き、より高速な使用効率100%の帯域占有型へと進化してきた。さらに、光ファイバを用いたギガビット・イーサネットも登場し、LANだけではなく通信事業者のバックボーンにまで使われるようになった(図1・表1)。
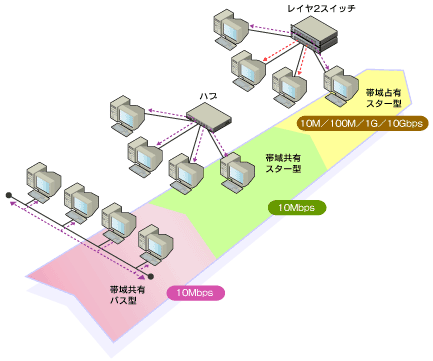 |
| 図1 イーサネット進化の歴史。当初、ネットワークの接続に同軸ケーブルが用いられていたころは、バス型のトポロジを形成していた。やがて、扱いやすいツイスト・ペア・ケーブルとハブが登場してくると、ハブを中心としたスター型の構成を取るようになった。そして、レイヤ2スイッチの登場により、帯域共有型のネットワークは帯域占有型のネットワークへと進化していった |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 表1 イーサネット進化の歴史的経緯 |
10ギガビット・イーサネットは、こうしたイーサネット技術を継承しつつ、ギガビット・イーサネットに比べさらに10倍のスピードを提供する最新のイーサネットだ。予定より若干遅れたが、2002年6月にIEEE802.3aeとして標準化が完了した。10ギガビット・イーサネットは、イーサネットの歴史上初めて、WANでの使用を前提とした技術も含まれる。もはや、「イーサネット=LAN」の常識さえも通用しなくなってきているのだ。
| Part.2 10ギガビット・イーサネットと従来技術との違い |
最初に、10ギガビット・イーサネットと従来のイーサネットに共通する部分を見てみる。まず、同じデータリンク副層 MAC(Media Access Control)を用いることだ。フレーム・フォーマットも同じだ。具体的には、6bytesの送信先MACアドレス、6bytesの送信元MACアドレス、2bytesのイーサネット・タイプに46〜1500bytesのデータ、4bytesのFCS(Frame Check Sequence)が付く。よって、最小フレーム・サイズが64bytes、最大フレーム・サイズが1518bytesとなる。10ギガビット・イーサネットでは、既存の技術から使えるものはなるべく流用し、開発コストと開発期間を抑えることを基本的なコンセプトとしている。
続いて、10ギガビット・イーサネットと従来のイーサネットで異なる部分を見てみる。まずは速度の違いだが、10ギガビット・イーサネットは従来のギガビット・イーサネットの1Gbpsに比べ10倍の10Gbpsを実現している。これは、LAN向けの仕様で「LAN PHY」と呼ばれている。10ギガビット・イーサネットにはもう1つ、これまでにはなかったWAN向けの「WAN PHY」と呼ばれる仕様もある。WAN PHYのデータ速度については、9.2942Gbpsとなっている。
また、10ギガビット・イーサネットの伝送モードは全二重のみだ。よって、半二重モードの制御に必要なイーサネット技術の基礎である「CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)」がMACから省かれている。伝送媒体としても、10ギガビット・イーサネットはマルチ・モード・ファイバ(MMF)あるいはシングル・モード・ファイバ(SMF)の光ファイバしか用いることができない。
|
10ギガビット・イーサネットでは、7種類の規格が標準化されている。以降の項目で、10GBASE-SR/LR/ER/SW/LW/EW/LX4と呼ばれる、7種類の規格のそれぞれの違いを解説していく(図2・3)。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 図2 10ギガビット・イーサネット規格の比較 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
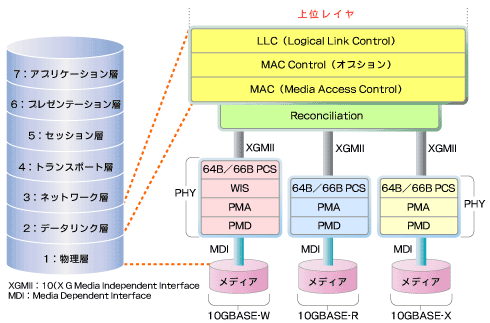 |
| 図3 10ギガビット・イーサネット規格の構成 |
これらの規格は、PHY(PHYsical sublayer)と呼ばれる物理層が異なる。まず、10ギガビット・イーサネットのPHYは、大きく「LAN PHY」「WAN PHY」の2種類に分けられる。LAN PHYは使用できるデータ速度が10Gbps、WAN PHYは9.2942Gbpsである。LAN PHYは、既存のギガビット・イーサネットを単純に10倍速したものになる。WAN PHYは、通信事業者のバックボーンで普及している10GbpsのSONET OC-192のフレームを流用することで、非常に安いコストでイーサネットをWANに適用することができる新しい技術だ。例えば北米では、インターネット・トラフィックの75%以上が通信事業者のSONET OC-192バックボーンを経由しているといわれる。WAN PHYでないとWANで使えない、という意味ではなく、「既存のWANのバックボーンにそのまま接続できる仕様」という意味だ。
LAN PHYからさらに詳細を見てみる。PHYは、PCS(Physical Coding Sublayer)と呼ぶデータを符号化する部分と、PMD(Physical Medium Dependent)と呼ぶ物理媒体に接続する部分から構成される。PCSとPMDはPMA (Physical Medium Attachment) により接続され、PMAではデータのシリアル化を行う。LAN PHYは、PCSにより10Gbpsのデータを64B/66Bと呼ぶ方法で符号化を行う10GBASE-Rと、10Gbpsのデータを2.5Gbps×4に分割し、それぞれを8B/10Bと呼ぶ方法で符号化を行う10GBASE-Xとに分けられる。符号化はデータ中の同一符号の連続を防ぐ方法で、64B/66Bで符号化すると、64ビットの情報が66ビットに変換される。よって、10GBASE-Rは10Gbpsのデータが64/66Bにより符号化され、実際の伝送速度は10.3125Gbpsとなる。同様に、8B/10Bを用いる10GBASE-Xは、8ビットの情報が10ビットに変換されるので、2.5Gbps×4が3.125Gbps×4となる。
10GBASE-Rでは、3種類のPMDを用いることができる。使用する3種類の光波長はそれぞれ、850/1310/1550nmとなっている。10GBASE-RのPCSとPMDとを併せた規格を、それぞれ10GBASE-SR/LR/ERと呼んでいる。Sは短距離(Short)、Lは長距離(Long)、Eは超長距離(Extended)を意味する。10GBASE-SRはマルチ・モード・ファイバ(MMF)を用いて最大300mまで、10GBASE-LRはシングル・モード・ファイバ(SMF)を用いて最大10kmまで、10GBASE-ERは同じくSMFを用いて最大40kmまで延ばすことができる。
10GBASE-Xは、PMDとしてWWDM(Wide Wavelength Division Multiplexing)技術を用いる。具体的には、1310nm付近を中心とした4波長(1275.7/1300.2/1324.7/1349.2nm)を用いて、3.125Gbps×4のデータを波長の異なる4波で送信する。10GBASE-XのPMDはこの1種類のみで、PCSと併せて「10GBASE-LX4」と呼ぶ。10GBASE-LX4には、MMF/SMFのどちらも用いることができる。MMFを用いると最大300m、SMFを用いると最大10kmまで延ばすことができる。
続いてWAN PHYの詳細を見てみる。WAN PHYは、10ギガビット・イーサネットで初めて登場した、WAN向けのイーサネット仕様である。WANの世界では最も普及しているSONET/SDHの仕様に合わせることで、イーサネットを簡単にWANの領域に適応することを目的としている。よって、最も単純にSONET/SDHのフレームにイーサネットのデータを載せる方法を採用している。SONET/SDHに完全に準拠しているわけではない。
WAN PHYは、9.2942Gbpsのデータを10GBASE-Rと同様に64B/66Bで符号化する。64B/66Bを用いるので、データ量が9.2942Gbpsから9.58464Gbpsとなる。この符号化されたデータを、WIS(WAN Interface Sublayer)と呼ぶ方法で9.58464GbpsのSONET OC-192のペイロードに埋め込む。この際に、SONETのスクランブリング(連続する同一符号の発生を防ぐ方法)が行われるが、データ量は変わらない。SONET OC-192では、制御情報を運ぶ各種のオーバーヘッドが付けられるので、実際の伝送速度は9.95328Gbpsとなる。言い方を換えれば、WAN PHYはSONET OC-192のフレームにデータを埋め込むために、データ速度がLAN PHYの10Gbpsとは異なる9.2942Gbpsになっているといえる。LAN PHYとWAN PHYでは、使用できるデータ転送速度が異なることが、最も大きな違いとなる。このPCSとWISを使うWAN PHYを「10GBASE-W」と呼ぶ(図4)。
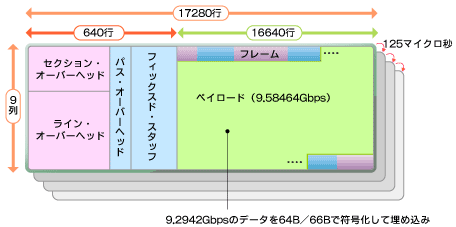 |
| 図4 WAN PHYのフレーム構造 |
10GBASE-Wは、10GBASE-Rと同じ3種類のPMDを用いる。使用する光波長は850/1310/1550nmの3種類で、それぞれ10GBASE-SW/LW/EWと呼ばれる。同様に、10GBASE-SWはMMFを用いて最大300m、10GBASE-LWはSMFを用いて最大10km、10GBASE-EWはSMFを用いて最大40kmまで延ばすことができる。
イーサネット・フレームには、先頭に7バイトのプリアンブルと1バイトSFD(Start Frame Delimiter)が付く。また、フレームは任意の間隔で並べられ、この間隔を「インターギャップ」と呼ぶ。インターギャップの最小間隔は12バイトとなる。フレームが最小間隔で続く状態がイーサネットの最大フレーム転送速度となり、この状態を「フレームがワイヤ・スピードで転送されている」と呼ぶ。先のデータ転送速度には、フレーム間のインターギャップとプリアンブル、SFDが含まれているので、実際のフレーム転送速度はさらに遅くなることに注意が必要だ。また、最大フレーム転送速度はフレーム・サイズにより異なる。
便宜上、「LAN PHYはLAN向けの仕様」「WAN PHYはWAN向けの仕様」と表現してきたが、実際にそれぞれの規格はどの領域に適応されるのだろうか。LAN PHYの場合、LANはもちろんのこと、10GBASE-LR/LX4は10km、10GBASE-ERは40kmまでの伝送距離があるので、MANにも適応できる。標準には含まれないが、PMDを変更すればさらに距離を延ばすことが可能だ。ギガビット・イーサネットの伝送距離も標準では最大5kmだが、ベンダが独自にPMDを変更することで、伝送距離100km程度のものが現実に使われている。新規にネットワークを作る場合は、LAN PHYでWANを構成することも可能となる。
では、WAN PHYはどこで必要なのか。最も必要となるのが、10ギガビット・イーサネットをDWDM技術によりさらに束ねる必要がある場合だ。DWDMでは、波長を入れたり出したりするために、光受動部品を多用する。これらを用いることで光損失が増え、結果的には伝送距離が延ばせなくなる。そこで、特に長距離用のDWDM光伝送装置では、距離を延ばすためにFEC(Forward Error Correction)と呼ばれる誤り訂正の技術を用いている。SONET OC-192の長距離DWDM伝送用に、FECと制御信号を併せてカプセル化を行う「デジタル・ラッパー」と呼ばれる技術が、すでに確立されている。デジタル・ラッパーは、ITU-T G.709 OTN(Optical Transport Network)の一部として標準化が進められている。もちろん最近では、MAN用のDWDM光伝送装置にもこのデジタル・ラッパーの技術が投入されている。LAN PHYとFECを組み合わせることも技術的には可能だが、実現するには非常に労力が掛かるので、この領域にはWAN PHYが適応されるだろう(図5)。
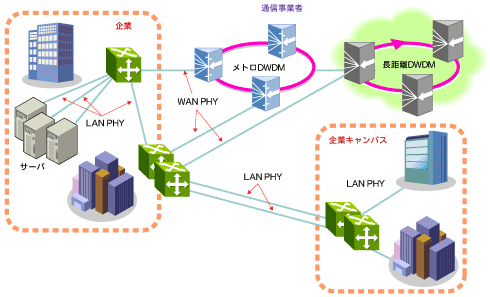 |
| 図5 10ギガビット・イーサネットの適応領域 |
| Part.3 10ギガビット・イーサネットの可用性を高める技術 |
少し前であれば、イーサネットに可用性を求めるのはナンセンスであった。ユーザーがLANに信頼性を求めていなかったわけではない。実際、多くのユーザーがLANでループを防止するためのスパニング・ツリー・プロトコルを用いて、ネットワークの冗長構成を取っている。特にLANのバックボーンでは、障害が発生した場合の迂回路を持つ構成が普通であった。ただ、スパニング・ツリー・プロトコルは障害時の切り替えに分単位の時間がかかり、とても信頼性が高いとはいえなかった。イーサネットは安価な技術であるため、それと引き換えに信頼性はある程度妥協されてきたのだ。ところが、最近では企業内のLANにおいてもイーサネット上で基幹業務のデータがやりとりされ、通信事業者の通信サービスを提供する技術としてもイーサネットが用いられている。もはやイーサネットだからといって、信頼性の低いままでは許されなくなってきた。コストを抑えつつ可用性を高めるという難題が、イーサネットに求められている。
だが、10ギガビット・イーサネットそのものに可用性を高める技術は含まれていない。可用性を高めるには、ギガビット・イーサネットと同様にレイヤ2スイッチの機能で解決しなければならない。その1つが、スパニング・ツリー・プロトコルを拡張し、障害時により高速に切り替えを行う方法だ。この技術は、ベンダ独自の手法によってレイヤ2スイッチに実装されてきた。現在、この技術は「IEEE802.1w ラピッド(高速)・スパニング・ツリー・プロトコル(RSTP:Rapid Spanning Tree Protocol)」として標準化が進められている。RSTPを用いることで、障害時の切り替えが秒単位(数秒〜数十秒)にまで改善される。
トポロジを限定することで、RSTPよりさらに高速に、具体的には1秒以内に切り替えるベンダ独自技術もある。ほかにも、IPネットワークの冗長に用いるVRRP(Virtual Router Redundancy Protocol)を、レイヤ2でも用いることができるように拡張したものがある。また、レイヤ2スイッチ間で複数本のイーサネットを束ねて用いることができる、リンク・アグリゲーションを拡張したものもある。ベンダ独自の技術は、ほかのベンダの機器と相互接続ができないという制限があるが、イーサネットの可用性を高める1つの選択肢となり、差別化のためにベンダも独自技術を競い合っている。
通信事業者が提供する通信サービスの可用性の目安としては、障害時に50ミリ秒以内に復旧することが挙げられる。レイヤ2スイッチで実現する秒単位の切り替えとは、けた違いの要求だ。こうした通信事業者の要求に応えるには、可用性を高める別の技術が必要となる。その1つが、IEEE802.17で標準化が進められている「レジリエント・パケット・リング(RPR:Resilient Packet Ring)」だ。
厳密には、RPRはイーサネット技術ではない。RPRは、これまでのイーサネットにはなかった帯域共有型のリング構成を提供する新しいMACの技術だからだ。RPRでは、イーサネットのIEEE802.3 MACとは異なる、まったく新しいIEEE 802.17 RPR MACを提供する。ただし、RPRの物理層に相当するRPR PHYは、既存の技術を流用する。具体的には、イーサネットとSONET/SDHをPHYとして流用する。イーサネットでは、光ファイバを用いるギガビット・イーサネット(1000BASE-X)と10ギガビット・イーサネットが用いられる。またRPRは、データリンク副層 MACより上位層の規定はないので、データリンク層としてIEEE 802.1D トランスペアレントブリッジ、つまりレイヤ2スイッチを用いれば、イーサネットとRPRをレイヤ2で接続することができる。結果的に、可用性を高めたイーサネットとしての使い方も可能となる。
RPRは、帯域を共有することでWANに必要な帯域の有効利用を図る技術のほかに、可用性を高める独自のRPRプロテクション(切り替え)技術を持っている。プロテクションとは、障害が発生した場合50ミリ秒以内に迂回する機能だ。RPRのプロテクション技術としては、2つの方法が検討されている。デフォルトとして検討されている「ステアリング」と、オプションとして検討されている「ラッピング」と呼ばれる方法だ。ステアリングでは、障害区間を発見すると、送信ノードが障害区間を避けてトラフィックを送出する方向を切り替える(ステアリング)ことにより、プロテクションを実現している(図6)。一方、ラッピングでは、障害区間を発見すると障害区間を避けてトラフィックを折り返す (ラッピング) 。ラッピングの方が単純で切り替え時間が早いので、ラッピング後にステアリングを組み合わせる方法も検討されている(図7)。方式はともかく、RPRを用いることでイーサネットでは実現不可能な通信事業者の要求を満たす50ミリ秒以内の切り替えを実現する。
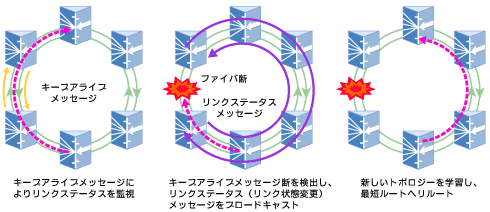 |
| 図6 RPRプロテクション — ステアリング動作 |
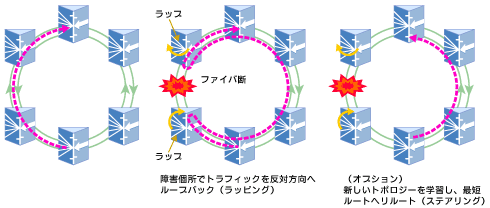 |
| 図7 RPRプロテクション — ラッピング動作 |
イーサネットの可用性を高めるもう1つのアプローチが、MPLS技術の活用だ。現在、MPLS網上でMACラーニング機能を持つマルチポイントのレイヤ2 VPN技術が検討されている。最近では、この技術を「VPLS(Virtual Private LAN Service)」と呼んでいる。
VPLSは、もともとは通信事業者がMPLS網を活用して広域イーサネット・サービスのようなレイヤ2 VPNを提供するための技術だ。VPLSがMPLS網上でレイヤ2スイッチをエミュレーション(仮想実現)する技術となるため、イーサネットの可用性を高める方法としても注目を集めている。VPLSは、MPLS網上でポイント・ツー・ポイントのイーサネットをエミュレーションする、「Martini」バーチャル・サーキットをフルメッシュで張ることにより実現される。フルメッシュが前提でダイレクトにあて先に届くため、エッジ部分にMACラーニング機能を持つことで、レイヤ2スイッチと同じ動作をする。個々にMACラーニング機能を持ち、ホップ・バイ・ホップのフォワーディングを行うレイヤ2スイッチネットワークとは、根本的に仕組みが異なる(図8)。
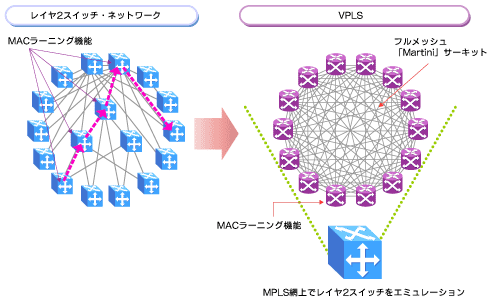 |
| 図8 VPLSの基本構成 |
MPLSでは、数多くの可用性を高める技術が検討されている。基本的に、MPLSは障害時にはIPのリルーティングにより経路の切り替えを行うが、これをさらに高速化する方法のことだ。その1つが、リルーティングまでにあらかじめ決めた迂回路を提供することで高速な切り替えを行うファスト・リルート方式だ。もう1つが、複数の経路をグループ化して、障害時にグループ内で迂回路を高速に選択するホット・スタンバイLSP(Label Switched Path)方式だ。これらの方式は標準化も進められ、切り替え時間の目標値として50ミリ秒以内を挙げている。RPRと同様にイーサネットとは別の方式であり、MPLSとVPLSの組み合わせで、イーサネットの可用性をより高めることができるようになる。
| Part.4 10ギガビット・イーサネットの最新動向と将来の展望 |
 |
| 写真1 WAN PHYを搭載したノーテルネットワークス製レイヤ2/3スイッチのデモ風景 |
10ギガビット・イーサネットの標準が「IEEE802.3ae」として承認された。これまで標準化に先行して製品を出荷してきたベンダに加え、年内にはさらに多くのベンダが標準に準拠したさまざまな製品の出荷を開始する。現状としては、先行出荷の製品を含め、レイヤ2/3スイッチにLAN PHYを実装したものが中心となっている。その用途として、ギガビット・イーサネットに代わる大容量のレイヤ2/3スイッチ間接続を意識しているものと思われる。
サーバ向けのアダプタも順次出荷されている。今後は、WAN PHYの実装やルータや光伝送装置などへの実装が進んでいくと予想される(写真1)。LAN PHY、WAN PHYの両方に対応するUNI-PHYや、PMDを交換することができるプラグ型のXENPAKの実装も徐々に進むだろう。ルータでは、現状でもかなり高価なOC-192 PoS(Packet over SONET)インターフェイスの代替が期待される。10ギガビット・イーサネットのWAN PHYとOC-192 PoSとには互換性はない。実現できる機能に差はないが、10ギガビット・イーサネットならば低価格化が期待できる。すでに多くの場で進められているが、異なるベンダの機器間で相互接続の実績が増え、10ギガビット・イーサネットが普及する環境が急速に整っていくだろう。
標準化が始まった当初は、通信事業者のバックボーンでWAN PHYの採用が先行し、その後にLAN PHYが普及するとみられていた。現状ではLANおよびMANでLAN PHYの採用が先行すると予想されている。多くのベンダがLAN PHYを出荷していることに加え、先進的なLANの構築やMANの高速化の需要が先行しているからだ。ただし、当初の予想より10ギガビット・イーサネット市場全体の立ち上がりは遅れている。理由としては、現状ではコスト的な魅力がないことが挙げられる。ギガビット・イーサネット10本分の価格より10ギガビット・イーサネットが安くなれば、普及が加速するとみられている。現状では、10ギガビット・イーサネットの方が数十倍以上は高くついてしまう。また、ギガビット・イーサネットを最大8本束ねることができるリンク・アグリゲーションが普及していることもあり、大容量化において10ギガビット・イーサネットによる明確な差別化が図れないことも挙げられる。
ただし、リンク・アグリゲーションは基本的にトラフィックをあて先ごとに負荷分散しているだけなので、1Gbps以上の帯域幅が必要なアプリケーションがあれば、10ギガビット・イーサネットのメリットが出てくる。シャーシ型の大型レイヤ2/3スイッチを例に挙げると、現状の製品では最大でもギガビット・イーサネット数十本を収容できる交換容量しか持っていないため、10ギガビット・イーサネットだと数本しか搭載できないものが多い。またスイッチの構造上、10ギガビット・イーサネットをワイヤ・スピードで処理できないものも多い。徐々にだが、10ギガビット・イーサネットの搭載を前提とした大容量の次世代レイヤ2/3スイッチも登場し始めており、今後の急激な市場拡大に期待したい。
10ギガビット・イーサネットのWAN PHYは、現時点では低コストでイーサネットをWANへ拡張する有効な選択肢となる。しかし、光伝送の世界で見ると、より高度にイーサネットと光伝送を融合する動きが見られる。その1つが、ITU-T G.7041として標準化が進められている「GFP(Generic Framing Procedure)」と呼ばれる方法だ。いわゆる「Ethernet over SONET」の技術の1つだが、WAN PHYにはない帯域幅の有効利用を可能とする。具体的には、バーチャル・コンカチネーションとLCAS(Link Capacity Adjustment Scheme)という技術とを組み合わせることにより、イーサネットをSONET上で伝送するだけでなく、SONET OC-192の中身を細かく分けて用いることや、ダイナミックに帯域幅を変えることもできるようになる。これらの技術は、光伝送を用いた次世代のMPLS技術である「G.MPLS(Generalized MPLS)」でも活用が期待される。またRPRでも、PHYとしてGFPを採用する予定だ。10ギガビット・イーサネットのWAN PHYは、イーサネットがWANに進出するための第一歩にすぎない。
イーサネット技術の1つとして、新たにLANとMANをつなぐアクセス・イーサネット技術「EFM(Ethernet in the First Mile)」の標準化がIEEE802.3ahで進められている。EFMが標準化されれば、エンド・ツー・エンドでイーサネットを接続する技術がそろうことになる。低コストでアクセス回線のブロードバンド化が実現できれば、やはり低コストでバックボーンを構成する10ギガビット・イーサネットへの要求がますます高まるだろう。さらに、イーサネットの高速化の要求はとどまるところを知らない。SONET OC-192より高速な「OC-768(40Gbps)」「OC-1536(80Gbps)」にイーサネットを載せる方法も検討されている。また、独自の100ギガビット・イーサネットの開発も始まっている。10ギガビット・イーサネットが普及を始めるころには、次のイーサネットの姿が見えてくるだろう。