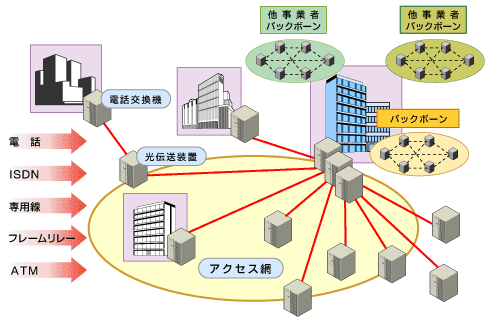
特集:MANと光伝送技術の最新トレンドを探る
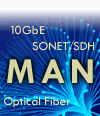
|
| Part.1 アクセス回線のブロードバンド化とメトロ・ネットワーク |
最近になり、家庭にも8MbpsのADSLや100MbpsのFTTHなど、これまでの56kbpsのモデムや64kbpsのISDNとは比較にならないほど高速化された、いわゆるブロードバンドのアクセス回線が普及してきた。企業向けでは、さらに高速な1Gbpsのイーサネットも、アクセス回線として提供されている。こうしたアクセス回線のブロードバンド化に伴い、当然そのアクセス回線を束ねる通信事業者のバックボーンも高速化する必要がある。これを支えるのが「MAN(Metro Area Network)」と呼ばれる最新のメトロ(都市圏)ネットワークだ。
アクセス回線の主流がISDNを含めた電話回線だったころは、現在の「MAN」と呼ばれるネットワークの多くは、156Mbps程度の回線容量を持った光伝送装置で構成されていた。そもそも日本では「MAN」という呼び方は一般的ではなく、単に「アクセス網」と呼ばれていた。同じ光伝送装置を用いて、電話回線だけでなく、企業向けの64k〜6Mbpsの専用線やIPを中心としたデータ系のトラフィックを収容するフレーム・リレー、ATMサービスのアクセス回線が多重されていた(図1)。
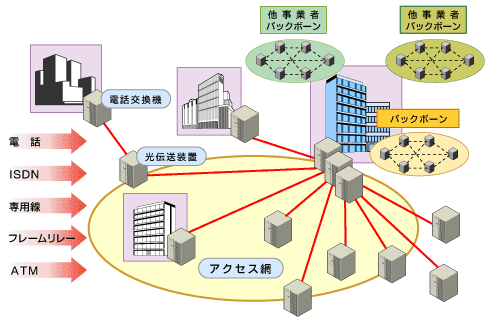 |
| 図1 アクセス回線の主流がISDNなどの電話線だったころは、MANは「アクセス網」と呼ばれており、電話回線のほか、専用線/フレーム・リレー/ATMのサービスなど、同一の光伝送装置を用いて多重していた |
アクセス網は、この区間に光ファイバを持っている限られた地域通信事業者によって作られ、この区間に光ファイバを持っていない長距離通信事業者などは、地域通信事業者のサービスを借りてアクセス回線を提供していた。この構成が一変する要因となったのが、アクセス網でのダーク・ファイバの開放だ。
これまでアクセス網を持っていなかった通信事業者も、ダーク・ファイバを借りて最新の光技術が投入された機器を接続することにより、高速で安価な自前のメトロ・ネットワークを短期間に構築することができるようになった。地域通信事業者に依存しないこの新しいネットワークは、「MAN」として注目されるようになった。
|
ビジネスが集中するメトロだけにターゲットを絞った新規通信事業者の参入もあり、「MAN」構築が通信事業者の間でブームとなっている。また、ユーザーへのアクセス回線もダーク・ファイバを用いることにより、例えばこれまでLANの世界で使われていた高速なイーサネットを、直接アクセス回線として非常に安価に提供できるようになった。こうして、多くの通信事業者がユーザーのアクセス回線からバックボーンまで、自前のネットワークでサービスを提供しはじめた。「MAN」の誕生は単なるネットワークの革新だけでなく、通信事業者が提供するサービスそのものの革新といえる(図2)。
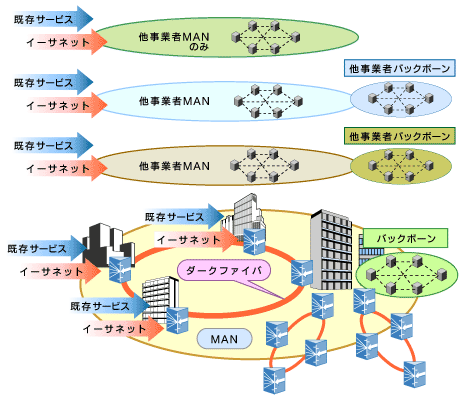 |
| 図2 ダーク・ファイバを用いることで、これまで一部の事業者のみが提供していたバックボーン〜アクセス回線のサービスを、さまざまな事業者が提供できるようになった |
| Part.2 WAN/MANを構成する光技術 |
現在、WANを構成する光技術はさまざまなものが用いられているが、基礎となるのはSONET(Synchronous Optical Network)/SDH(Synchronous Digital Hierarchy)だ。SONET/SDHは、電話回線などの低速な回線をTDM(Time Division Multiplexing)と呼ぶ方式で高速な回線に積み上げていく階層的な多重方式だ。SDHは、かつて日本、北米、欧州/アジア(日本を除く)で独自に用いられていた3つの多重方式を統一した世界標準であるが、北米では世界標準のSDHではなく、米国標準として決めたSONETを用いている(図3)。SONETとSDHは厳密には異なる部分もあるが、ほとんど同一の規格で、相互接続も可能だ。日本では、基本的にSDHを用いてきた。
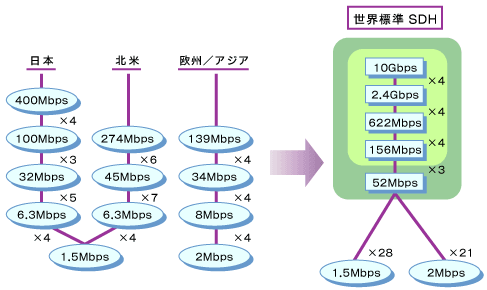 |
| 図3 それまで、日本、北米、欧州/アジアで用いられてきた別々の多重方式が統一されたのが、世界標準である「SDH」だ。ただ米国では、そのベースとなった「SONET」のほうが用いられている |
SONETは52MbpsのOC-1を基本に、SDHでは156MbpsのSTM-1を基本に、それぞれを階層的に多重する構造が決められている。後に、SDHでもOC-1相当のSTM-0が追加された。OC-1/STM-0は、電話回線1本分となる64kbpsを24本束ねた1.5Mbpsの回線を、さらに28本分多重したものだ。それを3本多重したものがOC-3/STM-1という具合に、高速側に多重していく。156Mbpsと表記されるOC-3/STM-1を例に挙げると、9行×270列(バイト)のフレームが125マイクロ秒間隔で送られるため、伝送速度は厳密には9×270×8÷125マイクロ=155.52Mbpsとなる。バックボーン・ルータなどは、1.5Mbpsなどの低速回線ではなく、直接SONET/SDHの高速インターフェイスで接続するPoS(Packet over SONET)を用いる。そうした場合に、ルータが使用できるペイロードはOC-3/STM-1を例に取ると、運用管理情報を運ぶためのオーバー・ヘッドを除く149.76Mbpsとなる(図4)。
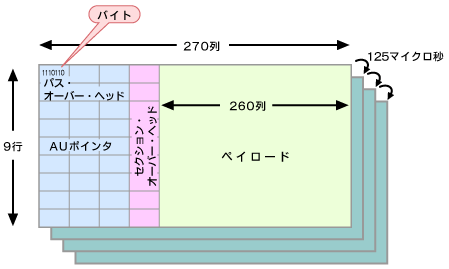 |
||||||||||||||||||||||||
| 図4 OC-3/STM-1におけるフレーム構造の例。伝送速度は、1bytes(bits)×270列×9行÷125マイクロ秒=155.52Mbpsだが、実際にデータとして利用できるペイロードは149.76Mbpsとなる |
SONET/SDHには運用管理に関する多彩な機能が含まれるが、その中でも最も重要な機能が、信頼性を高めるプロテクション(切り替え)機能である。有名なのは、SOENT/SDHをリング型に構成し実現する「リング・プロテクション」だ。光ファイバの経路としても、敷設区間が重ならないリング型に構成することで、信頼性が高いといえる。リング・プロテクションにはUPSR(Unidirectional Path Switched Ring)とBLSR(Bidirectional Line Switched Ring)と呼ぶ方式がある。
UPSRは、通常時にはリングの両方向へ現用、予備として同一のトラフィックを流し、現用に障害が発生した場合に受信側で予備に切り替える方式だ。「MAN」では、構造が簡単なUPSRが主に用いられている(図5)。
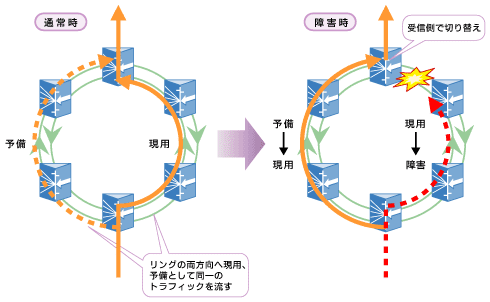 |
| 図5 UPSR方式では、リングの両方向へ「現用」「予備」として同一のトラフィックを流し、障害時に受信側で予備に切り替える |
BLSRは、通常時は現用として片方向へ流しているが、障害時はその区間を避けるように折り返して、反対方向で確保された予備を使って迂回する方式だ。どちらも、切り替えは50ミリ秒以内という非常に高い信頼性を提供するが、すべてのトラフィックを救済するには、SONET/SDHリングの半分の帯域しか用いることができない。BLSRは、障害時に救済を行わない代わりに、通常時に利用可能なエキストラ・トラフィックを運ぶこともできる。日本では一般的でないが、北米ではこうしたトラフィックを安いサービスとして提供している。
日本では、アクセス網に日本独自のSDH光伝送装置を用いてきたが、最近の「MAN」では、最新の北米製のSONET光伝送装置が非常に多く導入されている。北米の低速の基本速度が日本と同じ1.5Mbpsということもあり、SONET光伝送装置に日本向けの機能を若干追加するだけで、従来のSDH光伝送装置相当の製品として適応できるからだ。多くのSONET光伝送装置が既存のサービスを収容するだけでなく、ベンダ独自の方法でイーサネットを代表とするデータ系のトラフィックを収容できる。また、ダーク・ファイバを借りている通信事業者の場合は、同時に機器を置く場所も借りなければならないため、非常にコンパクトな北米のSONET光伝送装置が「MAN」の要件にフィットしたという事情もある。もともと北米では、SONET光伝送装置をユーザーのビルなどに置いて複数のユーザーを集めてくるアクセス回線の多重にも使っていたため、非常にコンパクトに作られているのだ。
現在の「MAN」では、最大でOC-48(2.4Gbps)あるいはOC-192(10Gbps)まで多重できる製品が主流となっている。長距離向けのSONET/SDH光伝送装置では、OC-192よりさらに高速なOC-768(40Gbps)などが開発されている。「MAN」では、より太い帯域幅が必要な場合は、もっと単純にOC-48/OC-192のSONET/SDHを別の方法であるWDM(Wavelength Division Multiplexing)技術を用いて多重する。WDMは、1本の光ファイバに異なる波長を持った信号を多重することで、光ファイバ当たりの伝送速度を増やす技術だ。多重には光カプラや光スプリッタといった、電気駆動を必要としない受動的な光合分波器などが用いられる(図6)。
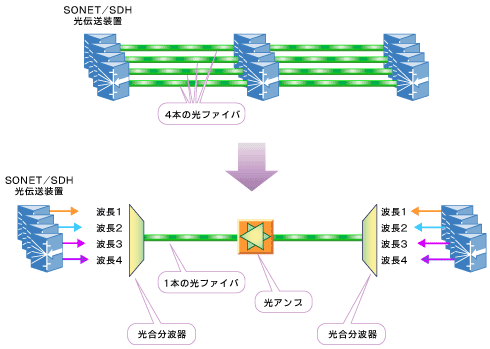 |
| 図6 WDMでは、複数の波長を1つの光ファイバに多重して伝送することができる。そのため、限られた環境でより太い帯域幅が得られる |
WDMは、多重できる波長数などによって区別されることがある。非常に多くの波長、具体的には16波以上を多重するDWDM(Dense WDM)、8波程度を多重するCWDM(Coarse WDM)、4波程度を多重するWWDM(Wide WDM)などだ。基本的に、多重する波長が少ないほど光関連部品の精度が悪くてもよいため、小型で安価な製品が提供できる。WDMは、「MAN」で必要な伝送距離を延ばすのにも向いている。光信号は、光ファイバを通る距離に従って減衰するため、伝送距離に制限がでる。WDMでは、光アンプと呼ばれる光信号を増幅する技術を用いて、多重したままの状態で一括して信号を増幅できるため、非常に簡単な構成で伝送距離を延ばすことができるのだ。
WDMは単に波長を変えているだけなので、イーサネットなど、SONET/SDH以外のどんな光信号でも多重できる。最近では、LANでおなじみのイーサネットとWDMとの組み合わせが「MAN」で積極的に使われている。ギガビット・イーサネットは標準には含まれないが、ベンダ独自で「MAN」で使用可能な数十kmの伝送を実現している。ギガビット・イーサネットとレイヤ2スイッチだけを用いたイーサネット「MAN」が、ダーク・ファイバを使って構築できる。さらにWDMを用いてSONET/SDHと多重することも可能というわけだ。
| Part.3 10Gbpsイーサネットの登場とRPR |
これまでのイーサネットがLANでの使用を前提に作られていたのに対し、IEEE802.3aeとして標準化される10Gbpsイーサネット(以下「10GbE」と略す)は、最初からWANでの使用を前提として作られているのが特徴だ。10GbEは、PHY(PHYsical sublayer)と呼ぶ物理層の違いにより7種類の規格が決められている。PCS(Physical Coding Sublayer)と呼ぶ符号化などの違いと、PMD(Physical Medium Dependent)と呼ぶ光波長などの違いの組み合わせだ。PMDの違いによって使用できる光ファイバの種類も異なる。規格の名称としては、それぞれ10GBASE-SR/LR/ER/SW/LW/EW/LX4と呼ぶ(図7)。
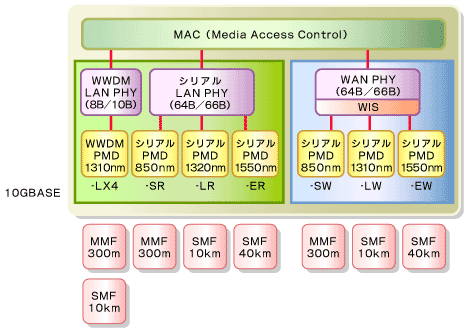 |
| 図7 10GbEでは、PHYという物理層の違いで7種類の規格が用意されている |
PHYには、ギガビット・イーサネット (以下「GbE」と略す) の速度を単純に10倍した10GbpsのLAN PHYと、WIS(WAN Interface Sublayer)と呼ぶ方式によりSONET OC-192フレームにデータを入れるWAN PHYの2種類がある。LANの環境とは異なり、WANではすでに通信事業者によって作られたネットワークがある。特に北米では、ほとんどの通信事業者の長距離バックボーンに、SONET OC-192を多重するDWDM光伝送装置が導入されている。SONET OC-192フレームを用いることにより、既存の設備にプラグ&プレイで接続できるのがWAN PHYだ。
LAN PHYの中でも「シリアルLAN PCS」は、10Gbpsのデータを64B/66Bと呼ぶ方式で符号化することにより、実際の伝送速度は10.3125Gbpsとなる。WAN PHYは、WISによりOC-192のペイロード(9.58464Gpbs)に64B/66Bで符号化したデータを埋め込むため、実際に使える帯域幅は9.2942Gbpsとなる。LAN PHYとWAN PHYで、使える帯域幅が異なることに注意が必要だ。LAN PHYには、WDM技術を用いたWWDM(Wide WDM)LAN PCSもあり、10Gbpsのデータを4つに分けた2.5Gbpsのデータを8B/10Bと呼ぶ方式で符号化することで、実際の伝送速度は3.125Gbps×4波長となる。
PMDは850nm/1310nm/1550nmを用いるシリアルPMDと、1310nm付近を中心とした4波長(1275.7nm/1300.2nm/1324.7nm/1349.2nm)を用いるWWDM PMDがある。マルチモード・ファイバ(MMF)、シングルモード・ファイバ(SMF)のどちらか、あるいはWWDMは両方を用いることができ、結果的にPMDの違いにより伝送距離が異なる。最大40km飛ばすことができ、「MAN」にも適用可能な伝送距離を提供する。さらに距離を飛ばすことのできるベンダ独自規格の製品も、一部出荷されている。
これだけ多くの規格があると使い勝手が悪いと思われがちだが、標準には含まれない便利な製品の開発も進められている。その1つが、「UNI-PHY」と呼ばれるLAN PHYとWAN PHYのどちらでも、設定などにより切り替えることができるチップセットだ。もう1つが、「XENPAK」と呼ばれる、GbEのGBICと同様にプラグ型でPMDを取り換えることができるモジュールだ。現在、先行出荷されている製品にはこれらの技術はまだ実装されていないが、今後出荷される10GbEはこれらを用いることにより、ユーザーは自分の使いたい規格に柔軟に変更することができるようになるだろう。
10GbEは確かに高速でWANにも適用できる技術であるが、GbEと同様にポイント・ツー・ポイントで帯域を占有する回線を提供するのみだ。長距離伝送においてはポイント・ツー・ポイントで飛ばすことも重要だが、「MAN」では多くの拠点で帯域を効率的に共有し、かつ信頼性を高める必要がある。こうしたGbEにも当てはまるイーサネットに足りない機能を実現するのが、IEEE802.17で標準化が進められている「RPR(Resilient Packet Ring)」だ。RPRは「MAN」で好まれるリング型のトポロジーを使用し、帯域幅を非常に効率よく用いながら、SONET/SDHと同様の50ミリ秒以内のプロテクション機能を提供する。
RPRは、すべての拠点間で共有するリング帯域幅の必要な区間だけを用いるスペイシャル・リユーズという方法で、全体として使用できるリング帯域幅を何倍にも拡大する(図8)。先に紹介したSONET/SDHのプロテクションは、単純にいえば半分の帯域を空けておく必要があるが、RPRでは、通常時はすべての帯域が使用できる独自のプロテクション方式を採用している。送信側でトラフィックを流す方向を決め、障害時は送信側で切り替えるステアリングと呼ぶ手法だ(図9)。またRPRには、イーサネットにはないサービス・クラスの概念が盛り込まれている。これは、あるユーザーに対してある帯域幅を保証するなど、ATMで実現されていた機能だ。RPRの物理層には、ほかの規格が流用される。候補として挙げられているのが、イーサネットとSONET/SDHだ。10GbEをリング型に接続し、信頼性の高い「MAN」を構成するという使い方も可能だ。
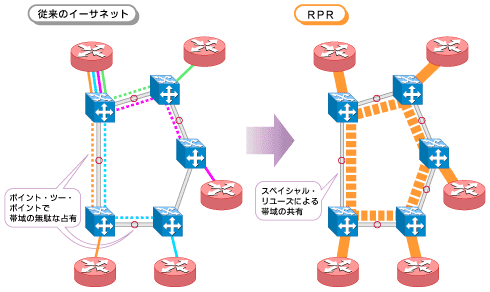 |
| 図8 RPRでは、スペイシャル・リユーズという方式により、リング内の帯域の必要な区間だけを用いることで、全体として使用できるリング帯域幅を何倍にも拡大できる |
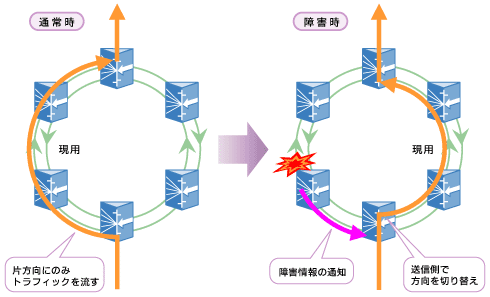 |
| 図9 RPRのプロテクションでは、SONET/SDHの場合とは異なり、片方向にのみトラフィックを流し(送信側で方向を決める)、障害時には送信側で方向を切り替える |
SONET/SDHも、10GbEやRPRに負けないさらなる進化を見せている。代表的なのは、ITU-T G.7041として標準化が進められているGFP(Generic Framing Procedure)だ。これまでベンダ独自の手法で行っていた「Ethernet over SONET/SDH」の標準化に加え、サーバやストレージ周りの独自インターフェイスであるファイバ・チャネル、ホスト周りのESCON(Enterprise System CONnection)、FICON(FIber CONnection)などを運べるように拡張する動きだ。WDM技術を用いれば、こうしたさまざまなプロトコルを多重することは可能だ。ITバブルの崩壊から、既存のSONET/SDHインフラを生かそうとする動きもあり、注目度が高まっている。
ただし、ここでGFPに従来のSONET/SDHをそのまま使うと問題が出てくる。GbEは1Gbpsだが、OC-12(622Mbps)に乗せるには足りないし、OC48(2.4Gbps)に乗せると半分以上が余ってしまう。この問題を解決するのが、SONET/SDHの基本単位であるOC-1(52Mbps)あるいはOC-3(156Mbps)を、任意の数で束ねて用いることができる「バーチャル・コンカチネーション」と呼ぶ技術だ。バーチャル・コンカチネーションを用いることにより、GbEは7本のOC-3(156Mbps)を束ねて非常に効率よく運ぶことができる。
また、これまでIPの技術であったMPLSも、イーサネットをはじめとするレイヤ2プロトコルを運ぶ技術として拡張に力を入れ始め、「MAN」を構成する技術の選択肢が広がってきている。こうして最新の光技術を見ていくと、「MAN」で覇権を得るためにイーサネット、SONET/SDH、WDM、IP/MPLSの技術が融合されていく様子が感じられるだろう。今後も、最新の光技術が投入される「MAN」に注目が必要だ。